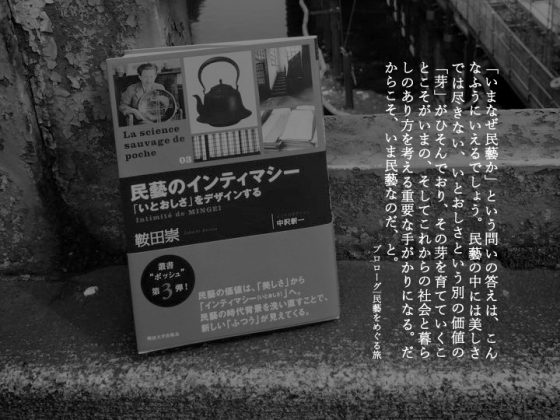会員公開講座 鞍田崇さん「民藝って何だろう」
12月24日、哲学者で明治大学理工学部准教授の鞍田崇さんをお招きして、本年度第5回目の公開講座が開催されました。鞍田さんは、近年、ローカルスタンダードとインティマシーという観点から思索を重ねておられます。今回の講座では、鞍田さんの思想活動のキーワードの一つ、「民藝」を取り上げていただきました。鞍田さんは、2015年に『民藝のインティマシー―「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会)の中で、“民藝の中にある「いとおしさ」を育んでいくことこそが、今、これからの社会と暮らしのあり方を考える重要な手がかりになる”ということを提唱されています。また、当塾と鞍田さんとのご縁を取り持つこととなった、就労継続支援B型事業所「ムジナの庭」(主宰・鞍田愛希子さん、伊東豊雄建築設計事務所が手がけた「小金井の家」をo+hが改修して2021年開業)でも、「民藝」の核心に通じる「平凡でいとおしい生活」支援のための活動に関わっていらっしゃいます。
今回の講座では、柳宗悦・岡本太郎・深澤直人さんらの言説を手がかりに鞍田さんが「民藝」の哲学を紐解いた過程について、お話を伺いました。
「民藝」との出会い
まず鞍田さんが画面に写したのは、京都の骨董街で手に取った刺子足袋の写真でした。表に施されたステッチに好感を抱き手を伸ばした足袋の裏面を見た時に、その使い古された生々しさに釘付けになったのだそう。その時の心情を「いきなり目の前に内臓・腑(はらわた)が突きつけられたようだった」とおっしゃいます。民藝といえば、機能性・実用性という点から美しさが語られがちですが、鞍田さんは「暮らしの中で使われてきたからこその、生々しさ」にいとおしさを感じていらっしゃるのだそうです。

加えて、「民藝」のゲイの字について、『サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。』(里文出版, 2011)という書籍を参照しつつ冒頭で補足いただきました。「植え育てる」という意味合いがある旧字体の「藝」の字に対して、新字体の「芸」には「草を刈り取る」という意味合いがあります。言い換えると、プロセスに眼差しを向ける『藝』に対して、ゴールに目を向ける『芸』の字。「民藝」を考える上では、完成した品のみならず、その成立過程をも大切にするとの含意があるのです。
「民藝」への熱視線
「民藝」運動が100周年を迎える節目を前に、「民藝」に注目が集まっています。柳宗悦の没後60年となる2021年には「民藝の100年」展(東京国立近代美術館)や、無印良品と日本民藝館連携企画「民藝 MINGEI 生活美のかたち展」が開催されました。
「民藝」という言葉がつくられたのは、1925年に遡ります。柳宗悦らが中心となり、身の回りの生活用品だけでなくこれからの社会や暮らしのあり方を問う運動の一環として「民衆的工藝」を略した「民藝」を提唱します。その翌年には、民藝美術館設立を目指す取り組みの一環として刊行された『日本民藝美術館設立趣意書』で初めて「民藝」が活字として紹介され、遂に1936年に日本民藝館設立に至ります。
この日本民藝館の5代目館長を務めるのが、プロダクトデザイナー 深澤直人さんです。深澤さんは、館長就任後のトークイベントで、パズルとそのピースとの関係を例に出しながら、「デザイナーの仕事は周囲の環境との調和を図りながらその場にふさわしいデザインを提供すること。一方で、パズル全体を俯瞰したときにその歪みが問題になる時、パズルそのものの歪みを正す重要な軸として民藝が参照できるのではないか」と説明されたとのこと。鞍田さんはこの言葉に強く共感したのだそうです。
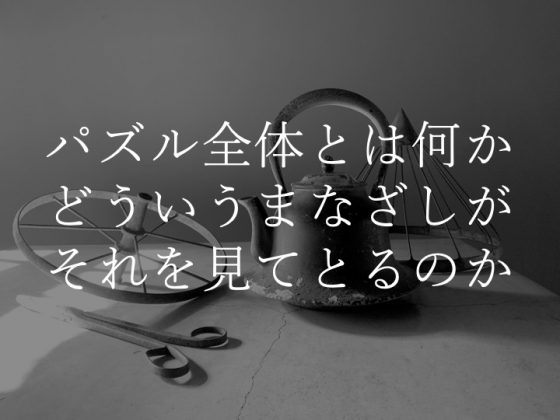
「民藝」を通して見えてくるもの
それでは、「民藝」が可視化しうる“パズルの全体”とはどういう姿なのでしょうか。“民藝運動の父”と称される柳宗悦は、「民藝」の「用と美」の有機的連関を強調しつつ、モノの実用性つまり“物への用”と、モノの美しさを表す“心への用”とが一体となり「民藝」品たる魅力を生み出している様を説明しています。加えて、民藝品の美しさの源として、人々の生活に不可欠であるという“全き用” を備えていることを説明しています。鞍田さんは、特にこの部分に面白みを感じたのだそうです。「“全き用”が基盤として存在しているからこそ、“物への用”と“心への用”が見えてくる」と理解すべきと鞍田さんは説明します。普通の生活や平凡さを肯定する価値観こそが、「民藝」が可視化しうる“パズルの全体”というわけです。
「民藝」に対してこのような眼差しを向けるのは、柳だけではありません。“ふつう”を深く考えながら活動するプロダクトデザイナーである深澤さんも、民藝品に備わる使い勝手の良さと美しさを踏まえつつ、「その上に立ち上る何かを強く感じた」と言及しています。
加えて、柳は“下手もの”つまり粗雑な日常道具から“生命の美”が垣間見えるという点も指摘しています。鞍田さんが京都で手に取った刺子足袋から感じた独特の生々しさは、まさに、美しさや厳しさを孕む生命・それが存在する日常生活が生み出すアウラだったのでしょう。

「民藝」の見方
柳は、世間的な価値に左右されずにモノの本質を見極める眼差しとして“直観”という概念を多用します。「見テ知リソ、知リテナ見ソ」つまり、知識でモノを見るのではなく、直に見ることの大切さを説いたわけです。鞍田さんはこれを「図ではなく地を見ようとする眼差し」と言い換えます。通常、私たちは図しか“見る”ことができません。地を凝視して“見えた”途端に、図となってしまうからです。同様に、知識も物事に意味を与える図的な作用で私たちに作用します。この認識方法から解放されたかたちでモノを受け止めるイメージとして、鞍田さんは“聴く”という認識を例に挙げました。「目は見たくなければ閉じることができる自覚的な感覚。一方で、聴覚は絶えず開かれていて、注意を向ける対象以外の音も拾う。いわば常に地に開かれている」と説明を加えました。
さらに、鞍田さんは、同様の眼差しを強調する人物として、文化人類学者としても知られる芸術家・岡本太郎を挙げ、そのルポルタージュ『忘れられた日本:沖縄文化論』(中央公論社, 1961)を紹介しました。岡本は、高度経済成長へと邁進していく本土が忘れてしまった“生命の感動”を沖縄に見出します。しかしながら、彼は、「生活そのものとして存在する生々しいモノが美的価値を見出され凝視される対象になった途端、その実態を喪失してしまう」からこそ、沖縄で見出したモノを美しいと言わないのだ、と明言するのです。
「民藝」の核心:親近感、愛着、インテマシー、愛し悲し美し
岡本の著作は「本来の生活が何らかの機会に剥き出しにされた時、我々は親近感を覚える、それは生き甲斐だからだ」という趣旨の言葉で結ばれます。鞍田さんは、この言葉に、やはり深澤さんや柳の感覚との共通性を感じておられます。例えば、深澤さんは、「民藝品に立ち上る何か」について「何かとは愛着・温かいもの」という説明もしています。そして、柳は「民藝」の世界にのめり込むきっかけともなった朝鮮半島の生活文化について、「親しさ・インテマシーこそがその美の本質にある」と言及し、民藝運動が本格化していく1927年には「親しさが工藝の美の本質」と説いています。
「一方で、柳が見ていた親密さは、実は悲しさと表裏一体だった」と鞍田さんは続けます。柳は、「古語では、愛おしをかなしと読み、美しという文字さえかなしと読んだ」と示しつつ、生きることには悲しみが常に付きまとうこと、それでも命を全うする生活に寄り添う品こそ美しく本質的に親しみが宿ることを指摘しています。「悲しみのみが悲しみを慰めうる。当時の朝鮮半島の厳しい情勢だけでなく、柳自身の不運な半生もまた、彼が『民藝』に悲しみと表裏一体の愛おしみ・美しさを託すきっかけとなったのかもしれない」という言葉で、講演は締め括られました。
岩永 薫