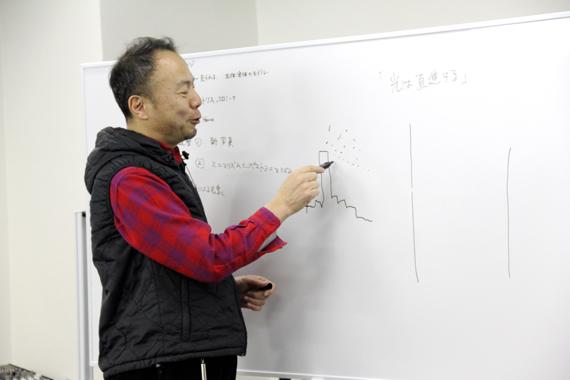講座A 畠山直哉氏「建築・写真」
2月24日、今年度最後となる講座Aは、写真家の畠山直哉氏を講師にお招きして開催しました。畠山さんは岩手県陸前高田市のご出身。伊東塾長がコミッショナーを務めた第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館では、畠山さんの撮影した「みんなの家」を中心とする震災前後の陸前高田の姿が展示され、そして見事金獅子賞の座を射止めたことは記憶に新しいでしょう。震災から間もなく2年が経ち、そしてビエンナーレの帰国展も開催されているこの時期に畠山さんのお話を伺えるのはとても貴重な機会であったと思います。
講義のおよそ1時間前から今回の講座の準備が始まりました。この日の神谷町スタジオは、電気を消すと真っ暗闇になるよう、全ての窓や光源を遮光シートで塞ぐ作業を講義前から有志の方に手伝っていただきました。いつもと少し様子が違うスタジオの中で、畠山さんの講義が始まりました。
去年、大阪の国立国際美術館にて行われた『写真の誘惑』というシンポジウムの際に、畠山さんは建築史家の五十嵐太郎さんから面白い話を聞いたそうです。それは、フランク・ゲーリーが彫刻と建築の差について「彫刻には窓がない。建築には窓がある。」と表現したというものでした。
今回全ての窓を塞いだのは、その言葉を確かめようと、“窓の体験”として「カメラ・オブスクラ」を実演するためでした。
「カメラ・オブスクラ」というものをご存知でしょうか?ラテン語で<暗い部屋>という意味で、私たちが普段使っているカメラという言葉の語源です。原理としてはピンホールカメラに似ていると言えばイメージし易いかもしれません。密閉した部屋の一方の壁に穴を開けて、外の景色を反対側の壁に倒立像として映す原始的な装置です。16世紀以前よりこの原理は知られていたそうですが、今回は神谷町スタジオをその舞台とし、原初的なカメラの体験を通して、“視る”ということ、客体=モデル−主体の関係、“写真”とは何なのか、直に感じ、考える機会を与えてくださいました。
今回の講義は、そのような写真というものについて、或いは写真と建築の関係について、今一度掘り下げて考える様々なヒントを与えてくれるような講義でした。“建築写真”が畠山さんの頭の中でどうなっているのか、2時間ではとても話し切れないということでしたが、その収まり切らない部分を想像しながら、参加者はそれぞれ色々な想いを巡らせたことと思います。
畠山さんは、建築と写真について、普通過ぎるほど普通の結び付きを持っていて、それほど頭を悩ませるほどのことではないと述べられました。写真が生まれた時から、その被写体として建築は撮られていて、それ以前はイラストレーションとして表現されていました。なぜなら、建築を言葉で表わすのはとても難しいからです。一方図像だと感覚的に理解できる。それは写真、また絵画やイラストがもつ特質です。例えばためしに建築雑誌のキャプションだけ取り出してその建築がイメージ出来るか、と問われました。しかし人間を説明するのは写真の方がかえって難しい、と畠山さんは付け加えます。
写真家の心理としては、カメラも建築である、と畠山さんは説明されます。それは体にも似ており、そこに共通するのは垂直性です。建築など垂直に屹立するものがあると、視覚的な抵抗感が生じ、挑戦したくなるのだといいます。自分たちが垂直に立っていることと、カメラのレンズや像が垂直方向であることには関係があり、建築を撮りたくなるのは、カメラの構造自体が自分たちの心理に働きかけているのではないか、と述べられました。そしてそれに対して、陸前高田は震災によって垂直方向の線が消えていく。空、陸、そして海しかないから、写真が撮れなくなる、と述べられた言葉は、重く心に響きました。
参考になるものとして、カメラ・オブスクラによる像を再度カメラで撮影するという作品を作る米国のアーティスト、ABELARDO MORELLや、『マスメディアとしての近代建築』という本で語られるル・コルビュジェの視ることへのこだわりなどを例に挙げられた後、写真と建築がどのように響き合っているか、そこで耳を澄ました時に「いい音」が聞えてきたら写真を撮る、聴覚で写真を撮るという感覚について語られました。建築写真は情報伝達の役目が一番だけど、それだけだと面白くない。「僕にとってカメラは完全に建築なんですよ。」と畠山さんはいい、“建築で建築を撮る”気持ちなのだと述べられました。
その後、LUCIEN HERVEとSTEPHAN COUTURIERという2人の仏人写真家について紹介してくださいました。エルベについては、コルビュジェがとても信頼していた写真家として、その部分を切り取るフレーミングの意識、写真家としてのモダンアートへの接近などに言及され、建物全体を撮るのを諦めることによって生まれる自由と、しかしそれでなお空間を表現するのが腕の見せ所と説明されました。エルベとコルビュジェの中には、写真を見るように建築やそこからの風景を見て欲しいという美学があったのではないかといいます。一方クチュリエの写真は、空を入れず、建築を真正面から捉えます。畠山さんはポスト・ミニマリズムとの関係を指摘されました。ファサードに相対して撮るという手法は80年代頃から一般的になり、90年前後から爆発的に増えるそうです。クチュリエはそのように増加した作品群を彼の“コピー”ではなく“クローン”と称したそうですが、その平面的手法によって、空間を平面に還元した時に起こる様々な出来事を映像に定着させます。建築をファサードに還元しているとも考えられ、建築を絵画的に見ていることに、なんだかゾッとする、とも畠山さんはおっしゃいました。
最後に畠山さん自身の撮った写真をいくつか紹介していただき、講義の方を締めくくりました。続いて質疑応答に移りましたが、2時間では収まらないと言われていた通り、ここでも話が尽きず、参加者からの様々な質問に答えているうちに、気がつけば講義が始まってから3時間近くが経っていました。
畠山さんにとって、写真は失敗しながら身に付けるものだったといいます。メディウムの限界を見極めながら、その手前ぎりぎりで何が出来るのか、どうすれば限界を押し広げられるのかを考えてきたので、いいこと尽くめのテクノロジーを前にすると途方に暮れてしまうのだそうです。しかし、技術が進歩し様々なことが可能になってきた現代ですが、実は何も変わっていないと畠山さんは指摘されます。デジタルにはなったけれども既存の写真術をなぞっていて、もっと新しい技術に伴う全く新しい発想が、今までのものを全部壊してしまうような何かが出てきてもいいのではないかと述べられました。
実際にものがあるかないかが関係なくなっているような洗練された表象操作環境の中、そこでのリアリティーとは何か、と畠山さんは問います。たとえば、目の見えない人にとって建築とはどういうものなのか。イメージと建築の関係に考えを巡らせながら、写真を通して、「実際に建っているモノに向かいたい。」「物と物の関係で何かが生まれると思いたい。」と語られました。
質疑応答が一応終了し、今回の講座が一旦締められても、畠山さんはまだまだ話し足りない様子で、その後も会場に残った方々と様々な談義に花を咲かせていました。長時間にわたって講義をしてくださった畠山直哉さん、ご清聴くださった参加者の皆様、特に遮光作業からお手伝いしていただいた方々に、厚く御礼申し上げます。
石坂康朗