伊東子ども建築塾 福岡 第6回『オノマトペのいえ』つくりながら、描きながら、考える①
6月28日(土)、観測史上初めて異例の速さで梅雨明けしたばかりの今日、伊東子ども建築塾 福岡の第6回が開催されました。
今回の授業は、中間発表後はじめての授業なので、まずは前回の振り返りからスタートします。

◆ 授業の主な流れ
・中間発表の振り返り
・レクチャー「Sence of Wonder」:末光弘和先生(SUEP./九州大学)
・「空間イメージ」から「いえ」に進化させていこう!
・タイトルに沿った物語を考える
・どこで だれと どのように いつ(朝昼晩 春夏秋冬)
中間発表の振り返り
まずは、担当TAと一緒に前回の振り返りからスタート。いろいろな意見が挙がって混乱したり、緊張からか言われたことをすっかり忘れてしまった子もいたようです。TAが受講記録をみながら、子どもたちにわかりやすいようにかみ砕いて補足しながら伝えます。

「Sence of Wonder 絵本の中に飛び込むように考えてみよう」
末光弘和先生(SUEP./九州大学)
中間発表後に戸惑う子どもたちの助け舟になったのが、末光弘和先生のレクチャーです。
末光先生は、かつて塾長である伊東先生のもとで働いていた時期があるそうです。伊東先生のアドバイスを補足するようなかたちで、ワクワクをかたちにする5つの方法について、末光先生の過去の作品に基づきながら教えてもらいました。
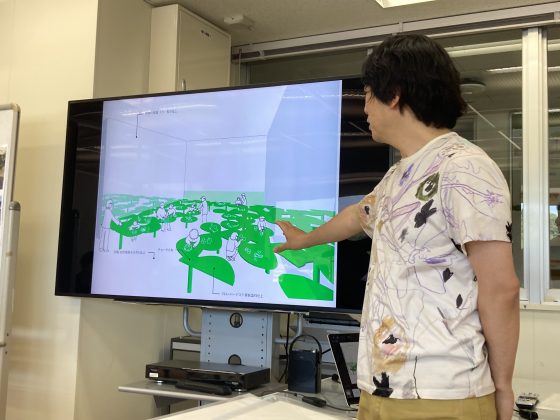
①こびとになって考えてみる:「クローバーのアートワーク」
これは、実際に咲いているクローバーのかたちをなぞりそれを25倍したかたちをそのままテーブルにしたアートワークです。スケールを変えることで、まるで人がこびとになったような体験ができます。テーブルは黒板の素材でできており、チョークで自由にお絵描きができるそうです。
②動物になって考えてみる:「地中の住処」
前回の四ケ所先生のレクチャーでも、動物の巣と“引き算のデザイン”について紹介がありましたが、末光先生からはその実例の紹介がありました。プロジェクト名は「地中の住処」。
③イメージを飛躍させてみよう:「そらとぶじゅうたんの家」
そらとぶじゅうたんをイメージして実際に建てた住宅の紹介がありました。絨毯のようにゆるやかにカーブするテラスは、子どもたちの絶好の遊び場になっています。
※②、③のプロジェクトの詳細は昨年のブログで紹介しましたので、ぜひご覧ください。
④〇〇のような家を考えてみる:「大きな樹のような家」
中央の壁柱を大きな木に見立て、5つのレベルがスキップフロアで展開されている室内。壁柱は樹木のように下階では小さく、上階になるほど大きくなり、ダイニング・リビングなど人が集まる部屋はオープンに、寝室などプライバシーが求められる場所では、囲まれた部屋になっています。壁柱を木に見立てることで、多様な場が生まれ、まるでツリーハウスのようなワクワク感がある住宅です。

⑤〇〇の気持ちになってみる:「百佑オフィス」
樹齢100年のマンゴーの木を残しながら、その周りにオフィスを建てるという最新のプロジェクト。人だけでなくマンゴーの木にとっても快適な環境を維持できるように、まずは樹木の計測と健康診断からスタートし、樹木への環境(水・風・光)等をシュミレーションしながら、建物の形を検討したそうです。そのプロセスは絵本になって今後出版されるとのこと。
人ではない〇〇の気持ちになって本気で考えてみると、また新しいいえの形が立ち現れてきそうです。
伊東先生が中間発表で言っていたこと「かたちにするのではなくビジュアライズ化する」「建築を内側から考える」「非現実から考える」とはどういうことなのか。
中間発表後、子どもたちだけでなく、TAや大人もその意図や手段についてあれこれ考えていましたが、末光先生から具体例をもってそのヒントをもらえた気がします。
レクチャー後は、大人も子どももなんだかすっきりした表情。
「空間イメージ」から「いえ」に進化させていこう!
中間発表を終えて、向かう方向は人それぞれ。
発表時のアドバイスやレクチャーをヒントに、もとの案がぐんと進化した子、おもいっきり飛躍した子、1つの言葉を追求して、そこからうまれた多様な在り方から全体をつくろうとする子、様々な様子がみられました。順にみていきましょう。

中間発表時、「雲の中で暮らす」というテーマを掲げていた子がいました。その際には、雲の中で暮らすことについて、もっと内側から突き詰めて考えてみようというアドバイスがありました。
雲というのは、可変的でつかみどころのない存在です。それを突き詰めて「いえ」にするという作業は、当初はとても難しかったようです。しかし、今回のレクチャーをきっかけに「雲の上に一本の木がある」という設定を思いつき、そこから雲の上で暮らすための多様な場のアイデアが次々に湧いてきたようでした。クレパスを持つ手も、おのずとどんどん進みます。
また、彼は雲の上という環境での暮らしを想像するなかで、従来の家具や家電のあり方にも目を向け、再構成を試みていました。たとえば、時計の代わりに朝を知らせてくれる「鳥小屋」をつくったり、テレビの代わりに外の風景を映す「テレビ型の小窓」を設置したりするなど、既存の道具を雲の上という文脈で捉え直していたのが印象的です。

一方、こちらの彼は教室に到着するなり、紙粘土で「手」の制作をはじめました。針金を通して関節が曲がるように工夫された、力作です。その後はTAと一緒に、風船に麻ひもを巻いて丸い「籠」をつくりはじめました。どうやら、先ほどつくった「手」がこの球体を支える模型をつくる算段のようです。
手で球体(主に地球)を支えるモチーフは、ギリシャ神話のアトラス像にも見られる比較的よく知られた構図ですが、彼がつくっているのは「ロボットの手」。ロボットの手が支えるその籠には、ワクワクするものがぎゅっと詰まっているようです。
つい深読みしてしまうのは私だけでしょうか。「人ではなくロボットが握る地球の未来?」などと考えてしまいそうになりますが、もしかするとそれは大人の視点にすぎないのかもしれません。子どもたちにとって、ロボットはもっと自然で、ワクワクを運んできてくれる仲間のような存在なのかもしれません。彼が今後語るストーリーに注目です。

また今回のテーマである「オノマトペ」から、ひとつの言葉を深く追求し、美しいドローイングへとたどり着いた子も印象的でした。
彼女が着目したのは「フワフワ」というオノマトペ。その響きに導かれるように、多様な素材や色を使って“フワフワ”の質感や雰囲気を丁寧に表現していきました。たった一つの言葉から、これほどまでに豊かな表現が広がることに驚かされます。
さらにその後は、フワフワ同士がどのように混じり合い、関わり合うのかという“関係性”にまで想像を広げていきます。クレパスで描いた色を、綿で優しくこすりながら混ぜ合わせる手つきは、まるで感覚と思考を同時に動かしているかのようでした。
すぐにかたちにするのではなく、立ち止まり、ひとつの感覚と言葉をじっくりと掘り下げる——そんな姿勢そのものが、彼女の表現の魅力になっているように感じます。
計算問題のように、明確な解法や正解さえもない課題を、子どもたちもTAも試行錯誤しながら取り組む様子が印象的でした。子どもたちが考えたストーリーがこれからどう発展していくでしょうか?
次回もお楽しみに。
古野尚美(ブログ担当)