講座A 福岡伸一氏「生命論から建築を考える」
2012年9月9日、伊東建築塾神谷町スタジオにて、生物学者の福岡伸一さんを講師にお迎えし、講座A「生命論から建築を考える」を開催しました。

講演タイトルは「生命を解くキーワード、それは“動的平衡”」。福岡さんの研究対象の一つである遺伝子は生命の“設計”図であり、それらを捉える生命観は「機械論」から「動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)論」へと変遷しています。
建築の“設計”への示唆も含めて、大変興味深いお話を展開いただきました。

まず初めに、福岡さんがセンス・オブ・ワンダー(自然の素晴らしさに目を見張る瞬間)に出会った「ルリボシカミキリと顕微鏡」や、そこから広がった興味対象である「レーウェンフックとフェルメール」等のエピソードについてお話しいただきました。
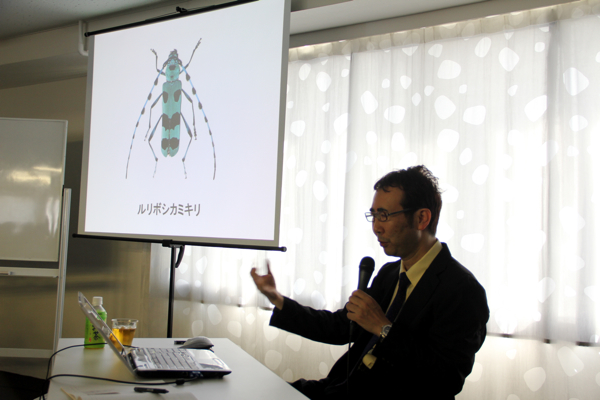
ルリボシカミキリはとても綺麗な青色の体をしており、自然界の青色が虫の背中に凝縮しているように見え、少年だった福岡さんの心を強くとらえました。しかしルリボシカミキリを顕微鏡で拡大しても青色ではなく無色透明であり、一定の短い波長のみ反射することにより青色に見えるという、光学的な青色だったのです。
そこから顕微鏡について興味を持ち、レーウェンフックという顕微鏡の製作者に辿り着きます。レーウェンフックは17世紀のオランダ・デルフト生まれで、日本でも人気の画家フェルメールも同時代のデルフト生まれです。レーウェンフックがロンドンの王立協会に送付した観察記録には詳細なスケッチが載せられており、「友人の画家が描いたもの」と記載されています。フェルメールが亡くなった翌年からスケッチの表現が変わったことや、フェルメールも光学的なアプローチをしていた画家であることからも、観察記録のスケッチがフェルメールのものである可能性が高いという仮説を紹介いただきました。
次に、顕微鏡によりミクロの扉が開かれた後のDNAの研究や生命観の変遷へと話を進めていただきました。
ヒトゲノム計画によりDNAの設計図が明らかとなり、生命は無限の神秘ではなく有限の分子となりました。遺伝子組換えや病気のメカニズムといった言葉に代表されるように、生命を機械のように扱うことが主流となります。
福岡さんもヒトゲノム計画の前から、細胞の中での遺伝子の機能を探り当てることを研究対象としていました。その一つがGP2タンパク質の設計図となる遺伝子であり、GP2を作り出せないマウスをつくり、異常を探り機能を発見するという機械論的アプローチによる研究を行っていました。しかしマウスには全く異常が見られなかったのです。
研究の壁にぶつかった福岡さんは、生物学者ルドルフ・シェーンハイマーの「生命は機械ではない、生命は流れだ」という言葉を思い出します。
彼の研究対象は、体内での食べ物の利用方法でした。機械論的アプローチでは、食べ物はエネルギー源としてガソリンのように消費されて消えていくと考えられていました。しかし、同位体(アイソトープ)により、食べ物の分子が体内でどのように利用されているかを調べると、半数以上の分子がマウスの体内にそのまま取り込まれ、一部に成り代わっていることが判明したのです。そして体内にいた分子が分解されて外に出て行っていたのです。生命のエネルギー源の取り込み方は、一部を交換する行為であり、ガソリンのように消費されるものではなかったのです。
生物学的には、生命体は絶え間なく流転しています。私たち生命とはプラモデルのような静的なパーツから成り立っている分子構造ではなく、パーツ自体のダイナミックな流れの中に成り立っている効果そのものであり、それが「動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)」なのです。
生命体は時間に対する秩序崩壊に対抗するために、一部を交換して秩序を保っています。ジグソーパズルのピースのように、互いに他を認識しながら成立する相補性を持ち合わせているため、一部が変わっても全体の絵柄は変わりません。そういった柔軟さを生命体は持ち得ていると言えます。例えば、機械論ではなく動的平衡論で先程の実験を見直すと、「GP2が欠落しているなりに、代替し、新しい平衡を立ち上げるよう変化している」と解釈し直すことができるのです。

レトロスペクティブに見ると、合理的に設計されているように見える生命も、ピースから生まれる発生的なものであり、これが設計への何らかのヒントになるのではなかろうかという示唆をいただきました。

例えば、丹下健三の東京計画では背骨のような軸があり、あばら骨を広げて機能が配置されています。また、青山学院大学の銀杏並木のメインストリートは、青山通りを超えて国連大学に軸が延びています。生命体は背骨からは作られることなく、ユニットが作られた隙間に骨が出来始めます。
しかし後から鳥瞰的に見れば、背骨が中心にあり、あばら骨や要素が付け加わっているように見えるので、人間の思考モデルは軸から考えようとしてしまいます。
また、伊勢神宮は20年ごとに式年遷宮を行うため生命的かと問われたことがあるそうですが、生命は少しずつ一部を取り換えているのに対して、伊勢神宮は全てのパーツを取り換えているので生命的とは言えないとのことでした。
最後に、建築が生命的であろうとするときに二項対立のコンセプトがあるとすればといった観点で、
①メカニズム・機械論・設計的・因果性
②メタボリズム・動的平衡論・発生的・共時性
を挙げていただき、伊東塾長や来場者の方々との意見交換に進みました。

(伊東)流動体としての建築というものを目指していたものの、以前は設計図としての流動体による空間的な建築を意図していましたが、現在はベネチアビエンナーレで提示したようなプロセス自体を重視した時間的な建築へと意識が変化しており、以前より動的平衡の考え方に近づいていけるのではないかと考えています。
(福岡)生命体には完成形と呼べるものがなく、若さという意味では受精卵がピークであり、その後の下りをなだらかにするために動的平衡が繰り返されています。建築のメタボリズムもカプセルより小さなレベルでの入替えができれば、本当のメタボリズムが実現するのではないかと考えます。
(伊東)建築のメタボリズムは機械論的で、インフラストラクチャーは変わらないもの、その先のエレメンタルなものを取り換えるということを謳っていました。小さな細胞が変わるという生物学的な意味では、現在の東京の姿そのものの方が、インフラは見えなくなるとともに小さな要素が変容しており、生命的と言えるように思えます。
(福岡)成長するにしたがって1年が短く感じると言われており、その理由には諸説ありますが、私は生物が持っている体内時計と外部時間のずれだと考えています。体内時計は代謝速度とリンクしており、代謝速度は受精卵が一番早く、その後ゆっくりになっていきます。成長すると体内時計が遅れていくのに、外部の時間は一定であるため、外の時間が早く感じるのではないかと考えています。社会的な時間の感覚としても、例えば縄文時代にはバームクーヘンのように少しずつ作っていく遺跡が残っており、完成させないことに意味があったと言われています。縄文時代は一万年以上も続いており生命的な時代や社会ともいえるかもしれません。
(伊東)個体の体内時計だけではなく、集住体としての都市や社会においても、体内時計のずれが生じているのかもしれません。
(福岡)都市から建築の話になりますが、壁や屋根などの構造は一旦作ると変えられませんが、生命体はどのパーツも細胞も交換することができます。つくった順番とは関係なく壊せるわけです。
(伊東)大工さんに相談し変更しながら建物を作っていた時代もありますが、現在は変更自体が間違っているという認識の下、変更できないシステムになっています。理想的な建築とは、完成形は一つの通過点に過ぎず、絶え間なく考えて、つくりながら、使いながら、変更しながら、次の目標に向かって進むものではないかと思います。そうすれば建築はもっと活き活きしたものになるのではないかと思っています。
(質問者)細胞が置き換えられつつも、なぜ古い記憶や鍛えた筋肉を保つことができるのですか。
(福岡)生命の階層には保存されるレベルと更新されるレベルがあり、更新される細胞レベルの上部に保存されるレベルがあれば、記憶や筋肉といった全体像は保存されます。建築も窓や壁などより小さなレベルで交換できれば、本当のメタボリズムができるのではないかと思います。
(質問者)動的平衡において破骨細胞のように壊す細胞の存在も重要かと思いますが、設計的・発生的という考え方から見るとどんなことが考えられるのでしょうか。
(福岡)生命体には作るよりも壊す仕組みの方が多重に存在しています。例えばタンパク質の作り方は一通りですが、壊し方は十通り以上あると考えられています。生物学的には、あらゆるものを壊せるのが若い人であり、壊せなくなるものが出てくるのが老化です。生物学的にはつくるより壊す方が重視されていることが分かってきており、建築史においても“作る”から“壊す”へのパラダイムシフトがあるのかもしれません。

福岡さんからは建築論と生命論を掛け合わせて様々な示唆をいただきましたが、保存レベルと更新レベルの再検討による生命的な建築・都市の可能性や、成熟した都市の老化を緩やかにする手法の一つとして“作る”から“壊す”へのパラダイムシフトといった考え方は大変興味深いものと思われます。
難しい分野を分かりやすくお話しくださった福岡伸一さんに深く感謝を申し上げます。
高田絵美
